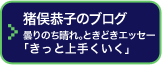猪俣恭子の物語
- 【プロローグ】 大学4年生時代
〜就活に達成感、のはずだけど〜 - 【エピソード1】 銀行員 本店営業部時代(前編)
〜企業は自分を磨く場〜 - 【エピソード2】 銀行員 本店営業部時代(後編)
〜思いは実現する〜 - 【エピソード3】 人事部研修グループ時代
〜研修センターは駆け込み寺〜 - 【エピソード4】 印刷会社現場奮闘時代
〜自分が変わるしかない〜 - 【エピローグ】 そして今、これから
〜思いは実現する。ビジョンには今を変える力がある〜
【プロローグ】 大学4年生時代
〜就活に達成感、のはずだけど〜
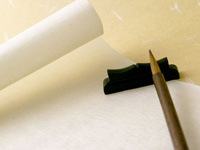
中央大学文学部史科国史学専攻、サークルは史蹟研究会、卒論は「幕藩体制展開過程に占める田沼政権の意義」、加えて無類の国宝好き。そんな『いっぷう変わり者』オーラ全開の私が就職活動で目指したのは、180度畑違いの銀行でした。具体的には地元の足利銀行です。
都市銀行入社一年目のOBに相談するも「絶対無理! 文学部の史学科で銀行〜?! なんで教職じゃないの、って思われるよ。無理だね。」と一刀両断。「じゃあどうすればいいんでしょう?」と尋ねると「せいぜいOB・OG訪問することだね。そうやってやる気だけでも見せれば。」とまったくもってつっけんどんな態度。でも、もうそれしかない、と藁をもつかむ思いで夢中で実践しました。
今でもありありと覚えているのは、集団面接のこんなひとこまです。「福田さんは汗をかくのが好きなんですか?(『スポーツ大好き』と書かれた履歴書を見て)」との面接官からの質問に「はあ、まあ、サウナが好きってわけじゃないですけれども。」と真顔で真面目に真摯に答えたところ、その場に居合わせた他の学生も面接官も一同大爆笑! (一人の学生さんは、ぶっと噴き出したときに勢いよく唾がとんでいました。)そんなキャラクターが面白がられたのか、無事、内定をもらうことができました。
さきほどのOBに内定報告をしたところ、「よく入れたな。うちの銀行ではありえないけど。」とあきれられました。そのOBが今や夫なのですから、人生というものはわからないものです。
何はともあれ、苦労して手に入れた銀行員。行く先、希望に満ちあふれるはずでしたが、ひっかかっていることがひとつありました。応募書類にも面接でも一貫して「営業店で窓口応対がしたい」と伝えていましたが、本当は人を育てる研修の仕事がしたかったのです。サークルでも後輩の面倒をみたり、声をかけたり、相談にのったり、そんなふうに相手を元気づけたり活気づけたりすることが大好きでした。だから本当は銀行でも研修の仕事がしたいのに、最後まで言えませんでした。銀行を志望しているのに「研修の仕事がしたい」なんて言ったら、「だったらうちの会社でなくてもいいじゃない。」と思われるんじゃないか、それだったら「営業店で仕事がしたい」と言ったほうが内定がもらいやすいんじゃないか、そう思ってもやもやとしたまま最後まで本心を隠していました。こんな私の気持ちを銀行側が察してくれれぱいいのに、そんな都合のいい期待を抱きながら・・・。
そして、卒業間近、銀行から届いた配属通知書には「本店営業部配属」。その文字をじいっと見ているうちに心がざわざわと揺れてきました。営業店で働くのか。そりゃそうだ。あれだけ営業店で窓口応対がしたい、って言ってきたんだから。希望がかなったっていうわけだ。でも、あれだけの事務処理のスピード、商品の勧誘、数字の達成、果たして私にできるのだろうか?
社会人への期待というよりも不安のほうがどんどんふくれあがり、気持ちが晴れないまま、新しい世界の扉は目の前で開かれたのでした。
【エピソード1】 銀行員 本店営業部時代(前編)
〜企業は自分を磨く場〜
入行して数日後に行われた新入行員導入研修は相当インパクトがありました。大げさかもしれませんが、あの研修があったからこそ、現場でどんなに辛いことがあってももう少しがんばろう、どうしても耐えられなくなったら研修センターのスタッフに相談しよう、そう思えるほどのものでした。同期同士、おちゃらけたり、真面目にディスカッションしたり、夢を語り合ったりしあった三日間。これから自分たちがこの銀行をもっとよくしていくんだという誇りと希望、そして現場でやっていくぞというモチベーションがあがり、私にとって本当にかけがえのない研修期間でした。
本店営業部では融資課第三係に配属となり、そこでの主な業務は住宅ローン、カードローン、マイカーローン、住宅金融公庫でした。営業部配属の新人は13人。この同期メンバーは先輩たちがうらやむほどの仲の良さ。ミスをして先輩に怒られてくじけたときなど、自然に集まっては「なに、くそ! いつか見返そう!」と励ましあっていたものでした。
とはいえ、新入行員のときはやはり精神的にかなりきつかったですね。職場でトラブルがあれば最初に疑われるのは新人。電話でお客様の社名を聞き間違って、そのお客様と連絡がとれず、大事な決済が絡む話なだけに上司からすごい剣幕で怒られたこともありました。神業のような先輩たちの事務処理のスピードについていけず「遅い!」といらいら声がとんでくるのは日常茶飯事。お客様にどうしても伝えたいことがあって勤務先に電話をしたら「会社に電話してくるな!」とクレームに発展。私の電話応対に不満を感じたお客様が「預金を郵便局に変えるからいいわよ!」と気分を害し、得意先係が菓子折りをもってすぐさま謝りにとんでいく。書類作成の不備がもとで期日に融資ができなくなり、これまた上司が住宅会社とお客様に平身低頭謝りに行く・・・などなど。大学4年生の我が世の春のように仕切っていた頃とはうってかわって、口癖は「すいません、すいません。」そればかり。どんどん自分が小さくなっていく感じがしました。
その一方で、こんなことも考えていました。預金係はほとんど定時であがれるのに融資は毎日こんなに遅くまで残業続きだ、それってどうなんだろう、ミスや欠点を指摘しあうこの雰囲気ってよくないんじゃないか、人を委縮させる一方だよ、仕事を教えるにもひとつひとつの作業の意味や書類の役割など背景的なものを伝えながらの指導のほうが、結果として早く仕事ができるようになっていくんじゃないか、と。
そこで、決意したんです。「私がこの職場を変えよう。」と。
融資係も定時にあがれるようにしよう、そしたら融資業務を担当したい人も増えるだろう、人のいいところやできているところを認めあう職場にしよう、自分が先輩になったら作業の背景的なところも新人に伝えていこう、と。そのために必要なことは何だろう。考えました。いずれにしても、私が「仕事ができる人だ」と周囲から一目おかれる存在にならなければ提案や意見を聞いてもらえないだろう。そう思うと行動はいたってシンプルになります。仕事のスピードアップのために取り扱い商品や業務知識は必要不可欠。また「福田さんの仕事は間違いない、確実だ。」と上司、先輩、お客様から信頼されることも大切。そこで休日にはオリジナルに作成したマニュアルや商品カタログを何回も読み直しました。さらに、様々な検定試験にもチャレンジしました。というのは、検定試験合格者は銀行内で発表になり、ある意味存在のアピールにもなるからです。もちろん勉強をすることで知識も深まりますから、事務作業ひとつひとつの決断も早くなりましたし、何よりも自信をもってきめ細かくお客様に商品の案内ができるようにもなりました。
ここまで書くと一人でがんばってきたようですが、もちろんそんなことはありません。本店営業部で仕事をしたのはたったの2年間でしたが、上司や先輩、同期には本当に恵まれました。周囲の応援があったからこそ今の私がある、しみじみそう思います。
たとえば、パーソナルコーチの増渕さん。増渕さんは、冷静沈着、書類の仕上げはパーフェクト、難しい案件になると必ず声がかかるほどで、上司からもお客様からも絶大に信頼されていました。それはそれでかっこいいし、頼りがいもありましたが、反面ちょっと近寄りがたい感じもして、それなりに気を使っていました。ある朝のことです。「おはようございます」と挨拶をしながら出勤される増渕さんは、いつもと違ってそわそわしているように見えました。席に座るなり、左隣の私のほうにくるりと身体を向けると、こう言います。「ねえ、福田さん、辞めるなんて思ってないわよね?」あまりにも突然なことに、私は「えっ」ととまどうばかり。「福田さんが『辞めたいんです。』って言っている夢を見たの。ああ、私がきつかったからかなあと思って。辛いことや悩んでいることがあったら、ためないで相談してきてね。」と。私のことを気にかけてくれる思いがまっすぐに届いてきて、とても嬉しかったですね。職場に自分の居場所ができたような、そんな安心感も生まれて「よーし、がんばるぞ。」とやる気がふつふつとわいてきた感覚を今でも覚えています。
また、直属の上司の佐藤さんにも本当にお世話になりました。佐藤さんは物静かにたんたんと仕事をされるタイプで、上司からの指示も、お客様からの苦情も依頼も、とにかく無理難題すべてひっくるめてスポンジのように吸収する人でした。佐藤さんのすごいところは、部下のミスや失敗に対して「なんでこうなった!」と感情的になったり、問い詰めることが全くなかったことです。(少なくとも私の前では)何かトラブルがおこると、「はい、私の出番です。お客様のところに行ってきましょう。」と薄い黒かばんをもって、いそいそとお客様のところに行かれる様子は、楽しそうにも見えました。とはいえ、きっと難しい案件も抱えて苦労もあったことと思います。けれども愚痴を言っている姿は見たことがありませんでした。その静かな姿からは「私の役割は部下を守ること」という決めも伝わってきて、だからこそ私たちも安心して大船にのった気持ちで仕事ができました。ちょっとでも困ったことがあればどんなことでもすぐ相談をしましたし、何よりも佐藤さんのために・・・という気持ちが課のメンバー5人にあったように思います。かっこいいことを言うと、この課で実績をつくって、佐藤さんを昇進させよう、のような。いまだに忘れられない思い出は、書類の不備で大失態をやらかして、ただただ謝るだけの私に「このお返しは福田さんの出世払いでいいですよ。」と穏やかに笑いながら言葉をかけてくれたあの場面。今でも思い出すたびに胸があつくなります。
私が目指したい上司像や先輩像の原点は、この本店営業部融資課第三係にあるといっても過言ではありません。人の感情、喜怒哀楽全部ひっくるめて、まさに「企業は自分を磨く場」。企業で働くことのダイナミズムを少しずつ少しずつ感じはじめた新入行員時代でした。
【エピソード2】 銀行員 本店営業部時代(後編)
〜思いは実現する〜
仕事ができる先輩たちに訊ねたことがあります。「将来、この銀行でどうなりたいんですか?」と。驚いたことに口々に返ってきたのは「早く辞めたい」でした。辞めたいと思いながら、こんなに仕事ができる? もしもやる気をもって働いたら、一体この銀行はどこまで数字が伸びるだろう? そんなことさえ思いました。やはり人事部で研修の仕事をしてみたい。仕事のモチベーションが高くなるような、やりがいを感じられるような、そんな研修をしてみたい。
そう思っていた矢先のこと。なんと定期預金の相談窓口に係替えになったのです。しかし、1年9ヶ月も融資のごく一部の事務しか担当したことがない私は、預金事務の流れはチンプンカンプン。窓口は二人体制でしたが、隣の先輩のほうがお客様応対のスピードが明らかに早い。ゆうに私の1.5倍もの件数は対応していたのではないでしょうか。後方事務の先輩は相当イライラし、「福田さん、遅い! もっと早くお客様の相談を切り上げて!」とカルトンと一緒にお叱りの言葉が飛んでくる、一人のお客様の応対時間が長くなれば、他のお客様の待ち時間も長くなります。にこやかにいらしたお客様のお顔も次第に強張り、目は吊り上がり・・・。「あとどれくらいでできますかっ!」
計算が合わなかった時のことです。「福田さん、何か心当たりない?」と課長代理に言われ、はて? と首をかしげたその時、思い出したのです! 記帳した伝票を間違ってゴミ箱に捨ててしまったことを! 慌てて地下の倉庫に飛んでいきました。90リットルサイズほどのごみ袋を思いっきり逆さまにして、両手で漁る、漁る。「あった!」しわしわになった伝票を後生大事に抱え職場に戻れば、上司からカミナリが。「なんだっ! 融資では伝票を捨ててもいいって教えられたのかっ!」申し訳ありませんと頭を下げて謝るのみ。ミスをしたあとのやり方を先輩に質問すれば、「そんなミスはしたことがないから、やり方なんてわからないっ」と不機嫌に。総務課の大先輩からは「福田さんが定期預金に移ってから、全体の計算が合うのが遅くなったのよっ」と怒り心頭。
さすがに落ち込みました。惨めでした。なぜ、他の人はできるのに私はこんなにもできないのか。能力が劣っているのだろうか。働くこと自体、適性がないんじゃないか。帰宅してからは同期に電話をかけ、事務フローのわからないところを教えてもらったりしました。
それでも日が経つにつれ、少しずつ預金事務のスピード感やお客様相談のコツも慣れてきました。「福田さん、頑張っているじゃない。いいんじゃない。その調子、その調子」先輩たちからそんな言葉をかけてもらえようになりました。とにかく慣れるしかない。とにかく間違いなく確実に仕事するしかない。信頼は自分で勝ちとらなければならない。
ささやかな自信らしきものがようやく芽生えた3月の下旬、人事異動発表の日。私には関係ないと、いつも通りに机に雑巾がけをしていました。が、遠く部長席がざわつき・・・。すると、「福田さん、異動だってよ」との声が。
本店営業部 福田恭子 異動先 人事部
人事部に異動? 私が? 雑巾を握る手が震えました。どきどきしました。入行してからの希望がかなったのです! 何人もの方から電話をいただきました。廊下ですれ違う方からも声もかけていただきました。「転勤、おめでとう」と。
数日たって、人事部研修グループの一期上の先輩から手紙が届きました。「このたびは異動おめでとうございます。私たち研修センター一同、福田さんと一緒に働けることをとても嬉しく思っています。今は、どうぞそちらでやるべきことに集中してください。そしてなんら心配することなく、こちらにいらしてください。楽しみにお待ちしています」読んでいるそばから、力が湧いてきました。「頑張ろう。異動を希望しながら叶わなかった人たちのためにも」
2年間の本店営業部時代。多くを体験し、学びました。その全てを活かすべく、働く舞台は本部に移っていったのです。
【エピソード3】 人事部研修グループ時代
〜研修センターは駆け込み寺〜
「おー、よく来たな」初出勤の朝、人事部研修グループ次長の小池さんの第一声。研修でお世話になった代理や先輩と並んで机に座るのは、不思議な感じでした。研修グループは全行員から見られるポジション。ちゃんと、しっかり、きちんとやらなきゃ。模範にならなきゃ。そんな私の様子を見て、次長はこう言ったのです。
「福田さん、私たちは先生じゃない。受講者が手を伸ばせば届く、研修センターのお姉さんでいなさい。一線で働く行員が迷って悩んで何かあったときに、最後に福田さんに相談にのってほしいと、そう思われる人でありなさい。研修センターは行員にとっての駆け込み寺なんだよ。私たち本部のお客様は営業店だ。営業店にとって役立つ研修は何かを常に考えなさい」
このことは、今でも私が講師をするときの大切なスタンスになっています。
さらに次長は折に触れ私に質問しました。「福田さんはどう思うんだ? ここで何をやりたいんだ?」
営業店で働いていたときは、そのようなことを訊かれたことはありません。だからいつもあたふたしました。都度、石井さんや金子さんと同じです、と答えるわけです。そのたびに次長は言いました。
「同じです、じゃなくて、福田さんはどう思うのかを聞いてるんだ。それがなければ、あなたがこの職場にいる意味はないよ」
私に答えがあることを信じている次長の気持ちが心に響きました。それに応えたいと、考えに考えに考えました。私がこの職場でやりたいことは何か。それからゆうに一年も経った頃でしょうか。ようやく伝えられたのです。「女子行員がもっと自分の力を発揮したくなるような職場をつくりたい」。そのときの次長の言葉は今だに忘れられません。「よーし、いいぞ。やれ」。素直に「よし、頑張ろう」と意欲が湧きました。
職場は、上司と部下という上下関係よりも対等な関係に。それも次長が大切にしていたことでした。Hondaのワイガヤ(役職や年齢、性別を越えて気軽に『ワイワイガヤガヤ』と話し合うという意味。)のような職場にしたいと。だからこそ、私たち女子行員も伸び伸びと仕事ができました。
印象に残っているのは、女子行員パワーアップ研修です。
研修グループの女性は私含めて3人。先輩の野澤さんと後輩の川田さん。私たちで新しく研修を企画し、それぞれが一クラスずつを担当するというもの。それまでは外部講師を招いての研修でしたから、画期的だったのです。3人で分担して内容を考え、共有しあい、資料も手分けして作り、少しずつプログラムを創りあげました。それでも時間が足りません。女子行員は残業が認められていなかったので、帰ったふりをして、更衣室で打ち合わせを続けたことも何回もありました。
その甲斐あって研修は成功。受講者からは、「このままでもいいやと思っていたけれども、自分も上を目指して頑張る。自分が後輩のモデルになる」、そんな感想が多く聞かれました。はつらつとした受講者をみて、責任を果たした安堵感と充実感でいっぱいでした。
次長もよく見ているもので「3人で遅くまで打ち合わせをしていただろう。よく頑張ったな」と。あれは本当に嬉しかったですね。
小池次長はその後転勤となり、代わりに赴任された次長たちは絵に描いたような管理職。職場は従来どおりの縦割型に戻りました。自由にアイディアが飛び交う、というよりは、ひたひたとした緊張感が漂う雰囲気になりました。“上”が変われば“職場”はまさに変わるのです。それを当事者として体験できたこともとてもよかったと思います。
その後結婚が決まり、県外に住むこともあって退職することにしました。多くの上司、先輩、後輩、同期に支えられての銀行での7年間。お給料をいただきながら、社会人としての基本、人間関係の創り方、仕事の取り組み方、チームとして仕事をしていくことの醍醐味、人としての在り方など、多くを学んだかけがえのない7年間でした。
【エピソード4】 印刷会社現場奮闘時代
〜自分が変わるしかない〜
退職後、地方銀行協会主催のインストラクター養成講座でご一緒した先生から連絡をいただきました。起業するので一緒にやらないか、とのお誘いだったのです。是が非でも一緒にやりたかった! でも、でも・・・! 丁寧にお断りしました。私の実家は印刷会社を営む自営業。父親は三代目。後継者として会社を手伝おうと思ったからです。年老いた父が営業やら工程管理やら納品までをやっている、その頑張っている姿を目の当たりにし、ほっとけなくなったのです。
当時、Macの登場により印刷業界は急速なデジタル化の最中にありました。ちょうど写植オペレーターの方が退職することもあり、私がDTPオペレーターになって穴埋めすることにしました。
しかし、銀行員時代にワープロしか使ったことがないのです。それがMacで版下制作、編集作業・・・と全く畑違いの仕事。取引先のモリサワの営業も「猪俣さんじゃ無理じゃないですか」とアドバイスをするほど。が、無理でもやるしかありません。
PCやアプリケーションソフトの操作や印刷の知識や技術の勉強づくめの日々。繰り返し繰り返しマニュアルを読みこみました。エラーやトラブルが発生すれば、モリサワのサポートセンターにすぐに電話をかけ、対処法を教えてもらいました。最終新幹線ぎりぎりまで残業することも続きました。ですが、後継者としてのプライドがあったのです。品質の高いものを提供したい、うちの会社にお願いすれば間違いなくやってくれると信頼される印刷会社になりたい。若手社員にDTPオペレーターを任せ、次第に営業として外にでるようにもなりました。
ただ、どうしても銀行で働いていたときを基準にして周りを見てしまう。お客様の応対や仕事の進め方、職場の整理整頓ひとつとっても、目にあまるところが多くありました。すると、自ずと口うるさくなるわけです。
ある日、若手社員に言われました。
「猪俣さんのやっていることは正しいです。でも、もっと私たちのことをわかってくれてもいいじゃないですか。」。ショックでしたが、それは事実。自分でも、なんとなくわかっていたのです。一人でからまわりしているな、と。自分の何かを変えなければ、ずっとこのまま。リーダーシップや人をどう育てるかの理論は知っている。けれども、実際に現場でできているかというと、この有り様。本当の意味で人を育てられる人になりたい、相手のモチベーションを上げられる人でありたい。そう思ってコーチトレーニングプログラム(CTP)を申し込んだのです。
CTPを受講して、一番はっとしたのは、「答えは相手の内側にある」という言葉でした。今までは、全て私が問題解決をしていました。そういう人が尊敬されると思っていたからです。しかし、いつでもそれがいいわけではない。相手がのびのびと考えられるよう、気づきがおきるよう、何をすればいいのか自分で見つけられるように「聞く」「質問する」「承認する」「フィードバックする」・・・。学んだことを必死に職場で活かしました。
一年ほど経ったころでしょうか。若手社員に言われました。「猪俣さんはうちの会社の要です。猪俣さんのビジョンを教えてください。私たちはそれをサポートしたいです」と。私を避けていた年配の営業の方は、営業先での情報を共有してくれるようになりました。愚痴ばかり言っていた現場スタッフは、トラブルが起これば自分が中心になって工場内で意見を調整してくれるようになりました。総務担当の方は、こう言ってくれました。「猪俣さんの負担が少しでも軽くなるように、私たちでできるところまで頑張ってやろう、って話し合っているのよ」と。社長の父は、「最近、ようやくリーダーらしくなってきたな」と。
自分のコミュニケーションのとり方が変わると、化学反応を起こすように周囲も変わる。それを確信した、かけがえのない体験でした。
【エピローグ】 そして今、これから
〜思いは実現する。
ビジョンには今を変える力がある。〜
職場のチームワークは随分と良くなったものの、経営は非常に厳しいものでした。
一方私は、人材育成の仕事がしたいという夢をあきらめきれず、中途半端なもんもんとした毎日を送っていました。父に相談しても「研修の仕事で生活ができるわけない。」と相手にされず、落ち込みました。さらに、夫の両親を相次いで見送ったこともあり、かなり気持ちが滅入っていました。
2005年。当時、小泉典子さんというコーチをつけていました。コーチングセッションで、彼女とこのようなやりとりがありました。
「猪俣さん、5年後にはどうなっていたいの?」
「そんな先のことなんかわかりませんよ。思い通りにならないのが人生なんです」
間髪いれず、小泉さんは言いました。
「そんなことを言っていたら、なんにもできないよっ!」
正直、少しカチンとしました。ならば、とやぶれかぶれになって語ったわけです。
コミュニケーション研修の仕事をしている、コーチの資格を持っている、CTPのクラスコーチをしている、コーチとして活動している私が新聞に載っている・・・! と。
いいね、いいね、と聞いていた小泉さんは最後に言いました。
「印刷会社の仕事を大切にしながら、猪俣さんがやりたいこともできるようにしましょうよ」
その瞬間、さあっーっと視界が開けました。そうなんです。今までは、「印刷会社の仕事を続けるか、それとも辞めるか」の二者択一しかなかったのです。でも、第三の選択肢が実はあった! 印刷会社の仕事をしながら、やりたいこともやる、という。
今の私がいるのは、あのときの小泉さんとの会話があったからこそ。
それからは、CTPで知り合った仲間と日本コーチ協会の栃木支部を立ち上げました。地元でコーチングや研修の仕事を始めました。起業もしました。反対するかと思った父も社員の方も応援してくれました。父にいたっては、屋号を一緒に考えてくれたり、商売繁盛を願って神社でお守りを買ってきてくれたりしました。
その父も病に臥し、会社のことを最後まで心配しながら亡くなりました。
税理士の先生と相談し、およそ100年近く続いた会社を閉じました。お客様には他の印刷会社さんを紹介し、安心くださるように配慮しました。惜しんでくださるお客様と会社を閉める最後の最後まで手伝ってくれた社員の方に有難さを感じつつの日々でした。
そして今。かなり遠回りしましたが、やりたいことにこうしてたどり着いています。
これだけの道のりを通ってきたことには、意味があったのでしょう。起きていることすべてには意味があります。今の自分にとってベストなことが起きています。
そう思えるようになったのも、小泉さんのあの「5年後はどうなっていたいの?」という問いがあったからこそ。将来に悲観的になっていた私が、ささやかながら未来を描けるようになった問い。今していることは未来につながっている、それを教えてくれた問いでした。
どうやら、やはり「思い」というものは「実現」するようです。ただ、本当に望んでいるのなら、ですが。
あなたは、将来、何をしていたいのでしょうか、どうありたいのでしょうか、何を持ち合わせていたいのでしょうか。ぼんやりとしたイメージからのスタートで構いません。
あなたの物語は、他の誰でもなくあなたが描くしかない。もちろん主人公はあなたです。人のキャリアというのはそうやって時間をかけて出来上がっていきます。
そんな思いを大切に、コーチとして、研修講師として、あなたがあなたの物語を自信を持って描けるように、仕事を通してこれからもサポートし続けていきたいと思います。